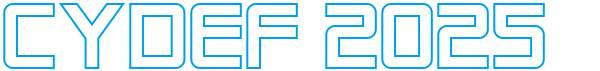各登録区分と聴講可能プログラム等の関係は以下のとおりです。
| 登録区分 | プログラム名等 | 特別会場 (クローズドエリア) | 一般会場 (オープンエリア) | オンデマンド配信 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room A | Room B | Room C | |||||||
| 基調講演 | 昼食 | パネルディスカッション | 机上演習 | ポスター(学術)発表 | 大使館・政府・大学・企業展示 | サイバー技術・先端研究紹介等 | |||
| Session 1-A-1 (日本) Session 1-A-3 (欧州) Session 2-A-1 (米国) Session 2-A-1 (インド太平洋) |
昼食時 | Session 1-A-2 (ACD) Session 1-A-4 (CIP) Session 2-A-2 (SEW) Session 2-A-4 (EDT) Session 2-A-5 (EDU) |
TTX-1 TTX-2 TTX-3 |
Poster Session 1 Poster Session 2 Poster Session 3 Poster Session 4 |
常時 |
Session 1-C-2
Session 1-C-4
Session 1-C-5
Session 2-C-2
Session 2-C-4
Session 2-C-5
|
特別会場(クローズドエリア)セッションのみ | ||
| オンサイト(現地会場参加)登録 | 特別会場(クローズドエリア)登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一般会場(オープンエリア)登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| オンデマンド(配信視聴)登録 | ✓ | ✓ | |||||||
12月9日(火) Day 1
| 9:00 ~10:15 |
Room A
Session 1-A-1 開会の挨拶 |
開会式・挨拶・基調講演(日本)
佐々木孝博 実行委員長(日本) 開会の祝辞
宮崎政久 防衛副大臣 基調講演
我が国のサイバーセキュリティ政策:昨今の状況と将来の課題について(仮題)
飯田陽一氏(日本):内閣サイバー官(併)国家安全保障局次長 アクティブパブリックープライベートパートナーシップ
横浜信一氏(日本):NTTセキュリティホールディングス CEO |
|---|---|---|
| 10:35 ~12:05 |
Room A
Session 1-A-2 |
「能動的サイバー防御:「能動的サイバー防御(ACD)における官民連携と防衛省の役割」
日本において能動的サイバー防御(ACD)の実施が正式に決定され、国家レベルでのサイバー対処体制が新たな段階に入りました。
その実効性を確保するには、官民の明確な役割分担と連携体制の構築が不可欠です。特に防衛省には、安全保障の観点から技術・制度・運用面での関与が求められています。
本セッションでは、ACDにおける防衛省の役割を含め、実効的な官民連携のあり方を検討します。
【モデレータ】
橋本豪氏(日本):サイバーディフェンスイノベーション機構 【パネリスト】
バーナード シーマン 博士(ベルギー):ベルギー王立エグモント国際問題研究所 |
| Room B
TTX-1 |
机上演習「CYDEFが実施するACD演習」 CYDEFは、多くの人が楽しんで参加できることを狙いとして、ACD対応-体験型演習(TTX)を開発をしました。参加希望者を対象に実施します。多くの人にとって楽しめるよう分かりやすく能動的サイバー防御のプロセスを体得できるものに仕上がっています。初級者の方も上級者の方も奮ってご参加ください。 (日本語のみ) |
|
| Room C
Session 1-C-2 |
CISSP チャレンジセミナー(短縮版)
淵上真一氏(日本):日本電気株式会社
(演題未定)
今野俊一氏(日本):フォーティネットジャパン合同会社
|
|
| 13:00 ~14:30 |
Room A
Session 1-A-3 |
基調講演(欧州)
変革ベクトル―危機管理の進化を推進するもの
コスタディン ラザロフ大佐(ブルガリア):NATO危機管理・災害対処研究所
ポーランド国防軍サイバーセキュリティ局の概要
パウエル ジウバ氏(ポーランド):ポーランド国防軍サイバーセキュリティ局長
国家主体による脅威への対抗:アクティブ・サイバー防御の活用
コンラッド プリンス氏(英国):元英国サイバーセキュリティ大使 BAE Systems Japan 合同会社
|
| 14:30 ~15:00 |
Room B Poster Session 1 |
ポスター発表(学術発表)
東京科学大学 笹原研究室 (日本語のみ) |
| 15:00 ~16:30 |
Room A
Session 1-A-4 |
重要インフラ防護:「重要インフラの防護とレジリエンスの確保」
重要インフラセクターとして、情報通信・金融、交通、エネルギー等様々な分野がありますが、これらのセグメントに所属する企業のシステムは、マルウエアによる障害の疑いがあっても、その影響範囲が大きすぎる為に簡単にシステムを停止して調査・対応することができない面が存在します。
また国内でサプライチェーンを完結できない場合は外国製製品を重要インフラに使用せざるを得ないというリスクも存在します。 本セッションでは重要インフラセクターの防護はどうあるべきか、何が必要か等を議論します。
【モデレータ】
ナタリー グラッツアー氏(スイス・オーストリア):NATOサイバー防衛協力センター
【パネリスト】
クシシュトフ ウィセク 博士(ポーランド):ポーランド軍通信研究所 |
| Room C
Session 1-C-4 |
災害対応におけるサイバー・セキュリティの課題と対策
花島誠人博士(日本):防災科研
日本をめぐる情報戦・認知戦の情勢について
長迫智子氏(日本):独立行政法人情報処理推進機構
セッション-CYDEFが実施するACD演習
仲間力氏(日本):Splunk Services Japan合同会社
|
|
| 16:30 ~17:00 |
Room B Poster Session 2 |
ポスター発表(学術発表)
法政大学 藤井研究室 (日本語のみ) |
| 17:00 ~18:30 |
Room A
Session 1-A-5 |
認知戦:「認知領域の安全保障」
経済安全保障のために、ナラティブ(物語)の果たす役割は近年急速に高まっています。これは、情報流通のための環境や、人々が情報を取り扱う方法の変化に基づいています。
ナラティブは、政治、文化と独立に議論することは難しいです。しかし、サイバー技術としてこれを扱う場合は、まずエンジニアリングとしてこれを扱う技術について検討することが必要です。
本セッションでは、政治活動や文化活動との関連の上で、ナラティブの安全保障上の価値を保全するための実践的な取り組みを検討します。
【モデレータ】
藤井章博博士(日本):サイバーディフェンスイノベーション機構
【パネリスト】
グンダルス ベルグマニス=コラーツ 博士(ラトビア):NATO戦略対話研究所 |
| Room B
TTX-2 |
机上演習「CYDEFが実施するACD演習」 CYDEFは、多くの人が楽しんで参加できることを狙いとして、ACD対応-体験型演習(TTX)を開発をしました。参加希望者を対象に実施します。多くの人にとって楽しめるよう分かりやすく能動的サイバー防御のプロセスを体得できるものに仕上がっています。初級者の方も上級者の方も奮ってご参加ください。 (日本語のみ) |
|
| Room C
Session 1-C-5 |
防衛省におけるサイバー人材等について 伊東寛博士(日本):国立研究開発法人 情報通信研究機構 金子順一3等陸佐(日本):防衛省 自衛隊 東京地方協力本部 募集計画班長 CCSP チャレンジセミナー(短縮版) (日本語のみ) |
12月10日(水) Day 2
| 9:00 ~10:05 |
Room A
Session 2-A-1 開会の挨拶 |
開会式・挨拶・基調講演
佐々木孝博 実行委員長(日本) 基調講演
実効性ある国家防衛のための新たな優先課題 文脈で読み解くサイバー安全保障 |
|---|---|---|
| 10:25 ~11:55 |
Room A
Session 2-A-2 |
宇宙・電磁戦:「新たな作戦領域としての宇宙空間」
近年宇宙分野のセキュリティ確保が重要視されています。多くの重要インフラを支えるシステムが衛星によるGNSS(Gloval Navigation Satellite System)からの信号を使用しており、これらの衛星は敵対国のKiller衛星の脅威にさらされています。またウクライナ紛争等で使用された長距離ドローン等もGNSS信号による航法を使用していたり、GNSS信号の偽装により民間航空機の運用に影響を及ぼす等の事例も存在します。また有事における海底通信ケーブルの切断時のバックアップとして民間通信衛星を利用する他国政府の動きもあるが、一人の大口株主の意向で利用の可否が決定してしまう民間通信衛星の利用には国家安全保障の面から考えた場合に問題も生じます。
地球観測産業において、ロシアは「交戦国が商業衛星を利用することは、軍事衝突への間接的な関与に当たる」と主張しています。デュアルユース、いわゆる「準民間」インフラは、報復攻撃の正当な対象となり得るとしています。 宇宙や電磁波領域でのセキュリティ確保がますます重要な問題となってくるものと推測され、本セッションでは宇宙・電磁波領域でのセキュリティ確保はどうあるべきかを議論します。
【モデレータ】
バルダオフ七重博士(日本):NATO国防大学
【パネリスト】
石井浩之 1等空佐(日本):航空自衛隊 宇宙作戦群司令 |
| Room B
TTX-3 |
机上演習「CYDEFが実施するACD演習」 CYDEFは、多くの人が楽しんで参加できることを狙いとして、ACD対応-体験型演習(TTX)を開発をしました。参加希望者を対象に実施します。多くの人にとって楽しめるよう分かりやすく能動的サイバー防御のプロセスを体得できるものに仕上がっています。初級者の方も上級者の方も奮ってご参加ください。 (日本語のみ) |
|
| Room C
Session 2-C-2 |
「プラス・セキュリティ研究所」における取組みと、セキュリティ諸団体連携での活動実績のご紹介 平山敏弘氏(日本):情報経営イノベーション専門職大学教授 更新のいらないセキュリティ対策 経済活動の安全性を確保するためにWebブラウザ内部を可視化するサイバー攻撃対策としてのブラウザセキュリティの再考 CCチャレンジセミナー (日本語のみ) |
|
| 13:00 ~14:30 |
Session 2-A-3 |
サイバーディフェンスの現状と課題(仮題)
アモーン チョムチョーイ 空軍中将 (タイ):タイ国家サイバーセキュリティ局事務総長 CMMC導入で進める戦略的サプライチェーン強靭化
ファン シール―博士(台湾):財団法人 国防安全研究院 サイバー・レジリエンスに関する研究開発
川口信隆博士(日本):株式会社日立製作所
|
| 14:30 ~15:00 |
Room B
Poster Session 3 |
ポスター発表(学術発表)
情報経営イノベーション専門職大学 平山研究室 (日本語のみ) |
| 15:00 ~16:30 |
Room A
Session 2-A-4 |
破壊的イノベーション:「量子時代におけるサイバーセキュリティ」
量子コンピューターによる暗号解読の危険性は20年先ともいわれる量子コンピューターの完成を待ちません。ハーヴェスト攻撃の脅威は現実的なものとして、それへの対策は喫緊の課題となっています。
Post Quantum Cryptography (PQC)は長年研究されていますが、まだ解決されていない課題を有しています。衛星量子暗号システムと統合した量子暗号鍵配送(QKD)ネットワークは地球規模のセキュア情報インフラ構築へのソリューションを提供しうるものです。QKDネットワークの社会実装により長期間の暗号の安全性と低レイテンシーの両立でき、PQCと共存してお互いの長所を生かしたシステム構築が可能となります。 本セッションではQKDネットワークとPQCを統合した量子時代の安全な情報インフラの構築に向けた現実的な検討を行います。
【モデレータ】
富田 章久博士(日本):元陸上自衛隊システム防護隊長 【パネリスト】
エマニュエル エアハード博士(オーストリア):クゥワンタムテクノロジーラボラトリー
キム ジェワン博士(韓国):韓国標準科学研究院 佐々木寿彦博士(日本):クオンティニュアム株式会社 花井克之氏(日本):東芝デジタルソリューションズ株式会社 |
| Room C
Session 2-C-4 |
災害レジリエンス強化のためのサイバー・フィジカル統合(CPS4D)の実現に向けた防災科研の取組
田口仁博士(日本):防災科研
ゲームを用いたレジリエンス構築
藤井章博博士(日本):サイバーディフェンスイノベーション機構 理事長
統合抑止における重要インフラ防護とTTX:リアルタイム可視化と自動対応で実現するレジリエンス
仲間力3等陸佐(退役):Splunk Services Japan合同会社
(日本語のみ) |
|
| 16:30 ~17:00 |
Room B
Poster Session 4 |
ポスター発表(学術発表) 法政大学理工学部応用情報工学科 藤井研究室 (日本語のみ) |
| 17:00 ~18:30 |
Room A
Session 2-A-5 |
人材育成:「安全保障を踏まえたサイバー教育」
サイバー脅威は技術的なもののみならず、認知的なものも含むものです。昨今の権威主義国からのSNS等を通じた影響工作は民主主義を根幹から揺さぶるものです。
本セッションでは、サイバー教育において、そのような脅威から国民を守るための取り組みを検討します。
【モデレータ】
桑名栄治博士(日本):情報セキュリティ大学院大学 学長
【パネリスト】
ヴァスコ プラテス大佐(ポルトガル):ポルトガルサイバー防衛学校長 |
| Room C
Session 2-C-5 |
防衛省におけるサイバー人材等について 伊東寛博士(日本):国立研究開発法人 情報通信研究機構 金子順一3等陸佐(日本):防衛省 自衛隊 東京地方協力本部 量子セキュアネットワークに向けたNICTの取り組み オンライン空間における偽・誤情報拡散とその影響分析:K Programを中心に (日本語のみ) |
|
| 18:30 ~ |
Room A
閉会式・挨拶 |
閉会式・挨拶
佐々木孝博 実行委員長(日本):広島大学法学部・東海大学平和戦略国際研究所客員教授 |
協賛
後援
大使館・
研究所・大学関係
助成
会場情報
| 会場名 | イイノホール&カンファレンスセンター |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング4階
|
| 電話番号 | 03-3506-3251 |
| URL | https://www.iino.co.jp/hall/ |